No.4 ロンドン留学時代の思い出 - Martin Raff 研での 3 年間 -
石崎 泰樹 群馬大学大学院医学系研究科
【留学まで】
医学科の学生時代から精神医学、神経科学に興味を持ち、東大脳研生化学の黒川正則教授が元精神科医であることから、1981年大学院は脳研生化学に入り黒川教授のもと、神経系細胞骨格に結合しているカルシウム依存性プロテアーゼの研究で学位を取得しました[1][2]。
大学院修了時には実験科学に興味が移り、学生時代から憧れていた江橋節郎教授(私の学生時代は東大医学部薬理学教授)のもとで修行すべく生理学研究所で1985〜1987年の2年間ポスドクを務めました。その時の研究テーマは当時未だ解明されていなかった軸索輸送の分子機構の解明でした。しかしながら実験を開始した直後に、Valeらが軸索輸送のモーター分子kinesinを発見し、まさに出鼻をくじかれてしまいました[3][4]。そこで植物の原形質流動の分子機構解明にテーマを変えて、Caulerpa(クビレズタ、近年は東京の居酒屋等で海ぶどうという名で供されています)を実験材料に選びました。Chara(シャジクモ)の原形質流動がアクトミオシン系に依存していることは以前より明らかになっていましたが、Caulerpaの原形質流動はチューブリンに依存していることが阪大の黒田清子先生によって明らかになっていたものの、モーター分子は不明だったからです。そこで沖縄県糸満市にある沖縄県水産試験場に交渉に行き、生化学実験に使える量のCaulerpaを提供していただくことになりました。到着したCaulerpaを早速ホモジナイズしてSDS-PAGE及び抗チューブリン抗体を用いたWesternブロットで解析したところ、肝心のチューブリンを検出できないことが明らかになりました。はじめは自分の技術を疑ったのですが、結局液胞中に充満しているプロテアーゼがホモジナイズの段階で解放されて、細胞質中に存在するチューブリンをたちまち分解するために検出不能となることが強く疑われました。その当時入手可能なプロテアーゼ阻害剤を数多く試しましたが、それらを組み合わせてもチューブリンは検出できませんでした。そこでウサギ骨格筋からのトロポニン調製の際、プロテアーゼ活性除去に有効であることが報告されているカゼインを利用したところ、ようやくWesternブロットでバンドが検出できるようになりました[5]。授乳される仔牛の栄養となるために分解されることが主目的と考えられるカゼインがプロテアーゼをトラップするため、チューブリンが保護されると考えられます。生理研時代には江橋先生の研究のお手伝いもしました[6]。江橋先生は骨格筋におけるアクトミオシン系がカルシウムによって制御されていることを明らかにし、カルシウム結合タンパク質トロポニンを発見するという大きな業績を挙げられていました[7]。カルシウムが細胞内のセカンドメッセンジャーとして機能していることの発見はノーベル賞受賞に十分に値する仕事であり、実際私が生理研に在籍している2年間でもノーベル賞の受賞者発表の時期が近づくと複数の新聞社からの取材があったのを覚えています。残念ながら江橋先生はノーベル賞を受賞されませんでしたが、カルモジュリンを発見された垣内史朗先生とともにノーベル賞を受賞されるべきだったと思います。江橋先生は生理研では平滑筋のアクトミオシン系のカルシウム制御機構の解明に取り組んでおられました。骨格筋ではアクチンに結合しているトロポニンがカルシウムを結合することによって、アクトミオシン系を活性化するというアクチン側の制御が行われています。江橋先生は平滑筋でもアクチンに結合しているトロポニンがカルシウムを結合することによりアクトミオシン系を活性化するというアクチン側の制御が存在するという説を立て、その立証に取り組んでおられました。ただ平滑筋では、カルシウムはカルモジュリンに結合し、これがミオシン軽鎖キナーゼ(MLCK)を活性化、活性化されたMLCKがミオシン軽鎖をリン酸化することにより、アクトミオシン系を活性化するという説が有力となり、現在教科書には概ねこの説が採用されています。私が研究者として大きな影響を受けたメンターは二人いますが、その一人がこの江橋先生です。江橋先生は、奥様とご一緒にほぼ研究室で生活し、研究所近くのご自宅にはただ寝に戻られるだけでした。江橋先生は、学士院会員をはじめ多くの要職についておられ、殆ど毎日のように東京出張があり、さらに学会関連のお仕事、生理研の所長業務など膨大なデスクワークをこなしつつ、私の知る限り、一日として実験室で電気泳動、遠心機操作、超沈殿実験をされない日はありませんでした。終電で東京出張から戻られた夜も、技官の実験ノートをチェックし電気泳動を仕掛けてお帰りになるのが常でした。江橋先生のお言葉で感銘を受けたものは数多くありますが、二つだけここに記しておきます。
・最近の若者は成果だけを気にしすぎる。我々の世代は実験することそのものに楽しみを見出していた。
・あまり論文を読んではいけない。オリジナルな仕事ができなくなる。
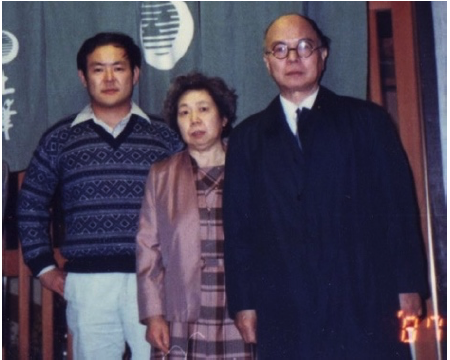
当時江橋先生は特定研究「血管の細胞生物学的、分子生物学的並びに代謝学的研究」を立ち上げられ、その研究分担者の室田誠逸教授が神経系の若手研究者を求めていたことから、1987年に私が室田研に赴任することになりました。室田先生はそれまで主として血管系でアラキドン酸代謝産物が果たす機能を研究してこられましたが、研究対象を神経系に拡張しようとされていました。私は室田研で細胞培養の技術を習得し、アストロサイト、脳微小血管内皮細胞等の初代培養系でアラキドン酸代謝、エンドセリン、一酸化窒素の研究を行いました。この頃、journal club用に文献を探していてたまたまMartin Raff教授のオリゴデンドロサイト前駆細胞の論文をまとめて読み、Martin(ラボの仲間は皆Raff教授を親しみを込めてMartinと呼んでいたので本稿でもMartinと呼ばせていただきます)のもとで研究したいと思い、江橋先生に推薦状を書いていただき、1991年にロンドン大学ユニヴァシティカレッジ(University CollegeLondon,UCL)のMartinの下に留学することになりました。当初は血液脳関門かグリア細胞の発生をテーマにしたいと考えていましたが、当時Martinの興味は細胞死に移っていて、私もMartinラボの他のメンバーと共に細胞死の研究をすることになりました。

【ロンドン留学時代】
UCL は、大英博物館から徒歩 10 分程度のところに位置し、大英博物館は入場無料なので、実験の空き時間には時々大英博物館を訪れました。留学当初は生物学部が入っていた Medawar Building (免疫寛容の発見でノーベル賞を受賞したPeter Medawar に因んで命名された)内の Martin のラボで仕事をしていましたが、途中からキャンパス内に Medical Research Council (MRC) Laboratory for Molecular Cell Biology が建てられ、Martin のラボはそちらに移ったので、私も留学後半はこの新しい建物で仕事をしました。留学中に Bernard Katz Building が建てられ、その中の Eisai London Laboratories の所長の Lee Rubin(現在 Translational Medicine at the Harvard Stem Cell Institute の Director)と Martin が一緒にラボミーティングを開催していたので、私も定期的にその建物に出入りしました。その後 UCL を訪れた時に、Andrew Huxley Building が建てられていて、神経生理学の著名な二人が UCL 縁の研究者であることを実感しました。

私のもう一人のメンターである Martin は、筋収縮のカルシウム制御を一筋に追 いかけておられた江橋先生とは対照的に、多岐にわたる興味の赴くままに研究 テーマを変え、その度に大きな発見をしてこられました(Martin の仕事全般につ いては彼がまとめたものをご覧ください[8])。もとはカナダマッギル大学医学部 出身の神経内科医でしたが(かのグレン・グールドの数少ない生演奏を聴いたこ とが彼の自慢でした)、米国マサチューセッツ総合病院で神経内科のレジデント をしているときにアメリカの徴兵制が変わり、カナダ国籍を有していてもベト ナム戦争に行かざるを得なくなり、アメリカから英国への移住を決意したとの ことです。英国ではロンドン郊外の Mill Hill にある国立医学研究所(National Institute for Medical Research, NIMR)で Avrion (Av) Mitchison(James D. Watson の 友人であり、Watson の“The Double Helix” の一部は Av の一家のスコットラン ドの別荘で執筆されたそうです。また Av の子息 Timothy (Tim) Mitchison も有名 な細胞生物学者で現在ハーバード大学教授です)とともに免疫学の仕事を開始 し、Thy1 がマウス T 細胞の表面にのみ存在し、B 細胞の表面には存在しないこ とから、T 細胞と B 細胞を識別・分離するのに抗 Thy1 抗体を用いるのが有効で あることを見出しました[9]。さらに B 細胞の表面にイムノグロブリンが存在し、 それが抗原刺激で一箇所に集まるキャッピング現象を発見するなど細胞生物学 分野で大きな業績を残しました[10]。その後発生神経生物学の研究に移り、オリゴデンドロサイトの発生に関して重要な発見をしました[11]。私が留学した当時は前述したように細胞死に興味を持っており、「細胞死は全ての高等動物細胞にとってデフォルトのプログラムであり、死ぬなというシグナルを他の細胞から 受け続けない限り細胞死のプログラムが起動する。」という説を立て[12] [13]、 私もロンドン留学中は彼の説を検証するための仕事をしました。
Martin に「自分の説の例外となるような細胞を探して欲しい。」と言われて、いろいろと考えた末に水晶体の細胞の生存調節を調べることにしました。水晶体は光が入ってくる方向に面した部分(前面)にある一層の上皮細胞層と、水晶体赤道部近辺で上皮細胞が分化してできる水晶体線維(後述するように、この分化にアポトーシスの分子機構が関与していることも明らかにしました)から構成されており、多くの他の器官とは異なり、ただ一種類の細胞のみを含んでいます。さらに水晶体は硝子体の中に浮かぶ孤立した器官で、血管・リンパ管支配も神経支配も受けないので、Martinの説の例外があるとしたら最有力候補であると考えたからです。幼弱ラットの水晶体前部から上皮細胞層をシートとして調製し、それをシグナル分子を含まないタンパク質不含培地中で培養すると、シート状の上皮細胞は長期間生存しました。このシートをトリプシン処理して上皮細胞をばらばらにしても、高細胞密度で培養した場合、タンパク質不含培地中で長期間生存しましたが、低細胞密度で培養した場合、短時間のうちにアポトーシスにより死滅しました。このアポトーシスは培地中に、水晶体上皮細胞が産生することが知られている IGF-1 及び FGF-2 を添加することにより阻止することができました。以上より、水晶体上皮細胞はその生存に他の種類の細胞からのシグナルは必要としないものの、同じ水晶体上皮細胞からの自己分泌性シグナルを必要とし、それが得られない場合はアポトーシスで自殺すること、すなわち水晶体上皮細胞も Martin の説の例外ではないことが明らかになりました[14]。次に軟骨細胞の生存調節を調べることにしました。軟骨もただ一種類の軟骨細胞から構成され、血管・リンパ管支配も神経支配も受けないので、Martin の説の例外の有力候補と考えたからです。軟骨細胞も水晶体上皮細胞と同様に、その生存に他の種類の細胞からのシグナルは必要としないものの、同じ軟骨細胞からの自己分泌性シグナルを必要とし、それが得られない場合はアポトーシスで自殺すること、すなわち軟骨細胞も Martin の説の例外ではないことが明らかになりました[15]。この後、線維芽細胞やいくつかのがん細胞の生存調節を調べましたが、Martin の説の例外は見つかりませんでした[16]。現在群馬大学で分子病態学の講義を担当しており、教科書として「ヴォート基礎生化学第 5 版」(東京化学 同人)を採用していますが、この教科書でも Martin の説が掲載されており(725ページの右カラム)、現在多くの研究者が信じているものと思います。 Martin は分子細胞生物学の教科書の中で最も定評のある“Molecular Biology of the Cell”の主要著者で、私の留学中は第 3 版を作成中で、James D. Watson をはじめ著者たちが Abbey Road に面した St. Johns Wood の一軒家で缶詰状態となってディスカッションするのを知り、著者たちのこのような意気込みがあるからこそ、あの魅力的な教科書ができるのだということを実感しました。
1994 年に東京医科歯科大学に戻ってからも、日本学術振興会の日英科学協力事業共同研究の支援を受けて、東京とロンドンを往復し、細胞死の研究を継続しました。このとき研究のテーマとしたのが、水晶体上皮細胞から水晶体線維への分化にアポトーシスの分子機構が関与しているか否かの検証でした。前述したように、水晶体線維は核やミトコンドリアなどの細胞小器官が失われ水溶性タンパク質クリスタリンが充満した細胞膜による袋状構造物です。上皮細胞から水晶体線維への分化の過程で失われる核の形態変化が、アポトーシスによる細胞死における核の形態変化(ピクノーシス)と非常に似ていることから、この分化にアポトーシスの分子機構が関与している可能性を疑いました。そこで先ず水晶体の凍結切片を TUNEL 染色したところ、分化過程にある細胞の核はTUNEL 陽性であることが明らかになりました。細胞がアポトーシスで自殺する際には PARP という分子量 116 kDa のタンパク質が caspase により限定分解を受け 85 kDa の断片が産生されます。ラット水晶体を出生直後から成体までの個体から摘出し、そのホモジェネートを抗 PARP 抗体を用いた Western ブロットで解析すると、出生直後の水晶体では 85 kDa のバンドは殆ど検出されず、生後 5 日目あたりからこのバンドが強く検出されるようになりました。また成体から摘出した水晶体を前部の上皮細胞層と、残りの水晶体線維から構成される部分に分けて解析すると、上皮細胞層では 85 kDa のバンドは検出されず、水晶体線維から構成される部分では 116 kDa のバンドは検出されず 85 kDa のバンドのみが観察されることが明らかになりました。以上より、水晶体上皮細胞から水晶体線維への分化に際しては caspase の活性化が起こることが強く示唆されましたので、caspase 阻害剤がこの分化にどういう影響を及ばすかを調べました。水晶体上皮細胞層をシート状に培養した場合、前述したように、シグナル分子を含まないタンパク質不含培地中でも長期間生存可能ですが、水晶体線維への分化は起こりません。培地中に IGF-1 と FGF-2 を添加すると、上皮細胞の増殖が促進されβ-クリスタリンの発現が上昇し(タンパク質不含培地中ではα-クリスタリンしか発現しません)、やがて上皮細胞層の上に lentoid body と呼ばれる球形の構造物が出現します。Lentoid body は無核の構造で、培養系で水晶体線維に相当するものと考えられています。この培養系に caspase の阻害効果を有する zVAD を添加するとβ-クリスタリンの発現上昇には影響を及ぼさないものの、lentoid body の形成が阻害されました。すなわち水晶体上皮細胞から水晶体線維への分化の一部には caspase の活性化が必要であることが強く示唆されました[17]。これは正常な分化に caspase が関与していることを示す最初の所見であると思います。

Martin のラボのラボ仲間で強烈な印象を受けたのが Barbara Barres でした。Barres は私が出会った中で江橋先生に匹敵するハードワーカーでした。朝研究室に行くと、実験室の床の上で寝袋に入って寝ている Barres を見かけるのがしばしばでした。Barres が私より先に帰宅することはありませんでした。また Martinに土曜日や日曜日の実験相談を持ちかけて、二人で長時間ディスカッションしていたようです(私自身は実験のスケジュール上やむを得ない場合を除いて、土日は休むようにしていました)。Barres は MIT で生物学の学士を取得後、Dartmouth College で MD を取得、Weill Cornell Medicine で神経内科の研修をした後、Harvard Medical School で神経生物学の PhD を取得して、オリゴデンドロサイトの研究をするために Martin のラボでポスドクをしていました。Barres はオリゴデンドロサイト前駆細胞(oligodendrocyte precursor cells, OPCs)の生存調節を検討し、OPCs はシグナル分子を含まないタンパク質不含培地中では高細胞密度で培養してもアポトーシスにより自殺し、PDGF 等のシグナル分子を添加して初めて長期間の生存が可能となること、すなわち OPCs はその生存に他の種類の細胞からのシグナルを必要とすることを明らかにしました[18]。Barres は生存調節以外にも OPCs に関していくつか重要な発見をし、スタンフォード大学にテニュアトラックポストを得て、アメリカに戻りました。群馬大学でテニュアトラック制度を導入する際、アメリカにおけるテニュアトラック制度について Barresから情報を得るために、2006 年 8 月にスタンフォード大学に Barres を訪ねました。Barres が性転換して Ben と改名したことは知っていましたが、実際に会ってみて Barres が髭を生やした男性になっていたことに少なからず衝撃を受けました。Barres はスタンフォード大学医学部神経生物学の教授として、シナプス刈り込みにおいてアストロサイト、ミクログリアの果たす役割の解明、血液脳関門においてペリサイトの果たす役割の解明等、神経科学の領域で大きな発見をし、数多くの優秀な若手研究者を育成しましたが、残念なことに 2017 年 12 月に 63歳の若さで膵臓がんにより他界しました。Martin による追悼文が Science 誌に掲載されているのでご覧ください[19]。他界直後の 2018 年 3 月に Barres 研出身の Richard Daneman と Nicola Allen を群馬大学に招聘して、彼らの最新の研究成果を紹介してもらいましたが、二人とも「Barres は非常に良いボスだった」と言っていました[20]。

ここまでロンドン滞在中のアカデミックな面を記載しましたが、非アカデミックな面にも触れたいと思います。私の趣味の一つは音楽鑑賞で、ロンドン滞在中はフィルハーモニア管弦楽団とロイヤルオペラハウスの定期会員になりました。フィルハーモニア管弦楽団の本拠地はサウスバンクセンター内のロイヤルフェスティバルホールで、最寄りの駅はロンドン地下鉄ノーザン線エンバンクメント駅であり、UCLの最寄り駅の一つであるノーザン線グージストリート駅からは乗り換え無しで短時間に行くことができました。当時の主席指揮者はジュゼッペ・シノーポリでしたが、一番印象に残っているコンサートはカルロ・マリア・ジュリーニの指揮したものでした。ロイヤルオペラハウスはロンドン地下鉄ピカデリー線のコベントガーデン駅で、UCLからはノーザン線のレスタースクエア駅で1回乗り換えるだけで行くことができました。当時の音楽監督はベルナルト・ハイティンクでした。私の席はamphitheatreという一番安価な席で、両側を体格の良いイギリス人に挟まれて、ワーグナーのニュルンベルクのマイスタージンガーのような長時間の演目を聞き通すのは、体力的に大変でした(今なら到底無理で、お金を出してもっと居心地の良い席を選ぶと思います)。とくに秋から冬にかけてのハイシーズンは殆ど毎週オペラ三昧で、楽しみであると同時に体力的には負担でもありましたが、それまであまり聴くことの無かったイタリア・オペラを数多く聴くことができたのは貴重な経験でした。最も印象に残っているのは、ルチアーノ・パバロッティがカヴァラドッシを歌ったプッチーニの「トスカ」で、その明るく輝かしい高音には圧倒されました。オペラと言えば、グラインドボーン歌劇場でモーツァルトの「コジファントゥッテ」を見たのも良い思い出です。結構苦労してチケットを手に入れ、ロンドンのビクトリア駅から鉄道に乗り、ルイス駅で降りて、バス等を乗り継ぎ、苦労してオペラハウスにたどり着いたのを覚えています。自分としては上下揃いの背広を着用し精一杯正装して出かけたのですが、男性聴衆の殆どがディナージャケット(タキシード)を着用していて非常に肩身が狭い思いをしました。幕間には広い庭園でサンドウィッチを食べたりして、ロイヤルオペラハウスでのオペラ鑑賞とは全く別世界の出来事でした。この他にウィグモアホールにもしばしば通い、マリア・ジョアン・ピレシュの弾くシューベルトのピアノソナタの夕べが印象に残っています。バービカンセンターにも時々行って、アーノンクールが指揮したモーツァルトの後期交響曲演奏会(当時は独特のフレージングに馴染めずあまり楽しめませんでした)、ロストロポーヴィチによるバッハの無伴奏チェロ組曲全曲演奏会(これも私の好みではありませんでした)などが印象に残っています。他にはグスタフ・レオンハルトが指揮してバーバラ・ボニーが歌ったJ.S.バッハの「コーヒーカンタータ」、J.E.ガーディナーが指揮してアンネ・ゾフィー・フォン・オッターとシルヴィア・マクネアーが歌ったモンテヴェルディの「ポッペアの戴冠」(内田光子が聴きに来ていました)、1992年がヘンデルの「メサイア」のダブリン初演250周年にあたるということで演奏されたJ.E.ガーディナーの指揮による「メサイア」などに大きな感銘を受けました。もちろん夏にはロイヤルアルバートホールでのプロムスも楽しみました。1993年の夏には苦労してラストナイトのチケットを手に入れ、イギリス人が熱狂的に歌う“Rule, Britannia!”に圧倒されました。ロンドン留学中は大学の業務から開放され、UCLでは研究のみに集中でき、留学前に未だ小さかった子どもと一緒に見ていたNHKの「おかあさんといっしょ」の中で歌われていた「のんびり・のびのび」の一節「のんびりのびのびじかんはたっぷり」と小声で歌いながら実験していたのが懐かしく思い出されます。
【最後に】
Martin には何度か群大で講演をしていただきましたが、学生・若手研究者向けの講演で彼が述べたアドバイスをご紹介いたします。
Some advice for young scientists
- Maximize your chances of discovery
- Be bold: address important questions
- Avoid crowded areas of research
- Try to kill your current hypothesis quickly
- Make time to think
- Share everything – reagents, mice, ideas
- Publish small steps, if they are important

RichardとAllenによるとBarresも「重要な問題だけに取り組め」という方針だったようです。「論語」の「為政第二十五」に「学而不思則罔、思而不学則殆。」とあります。「学びて思わざれば則ち罔(くら)し、思いて学ばざれば則ち殆(あやう)し。」です。この「思う」というのは「何が重要かを意識する」ということだと思います。「学ぶ」は一般的には「これまで築き上げられてきた客観的体系を学ぶ」ということだと思いますが、研究の場合は「文献を検索すると共に、実験することによって『自然』から学ぶ」に置き換えても良いのではないでしょうか?そうするとこの文章は「いくら文献検索の上、たくさん実験しても何が重要かを認識していない場合は実りある結果は得られない。いくら何が重要かを認識していても、文献検索から得られた情報をもとにしっかりとした実験計画を立てて、それを実証する実験結果が得られなければ、やはり何にもならない。」と解釈できます。Martinのアドバイスの1、2はこのことを意味していると思いますが、「何が重要かを意識する」のは難しいことだと思います。Martinのアドバイスの5は「何が重要かを意識するために考える時間を設けなさい。」という意味だと思います。7も非常に大事なアドバイスだと思います。私はもう2021年3月に大学をリタイアしますが、若い研究者の皆様にはMartinのアドバイスを噛みしめていただきたいと思います。
【参考文献】
- Ishizaki, Y., T. Tashiro, and M. Kurokawa, A calcium-activated protease which preferentially degrades the 160-kDa component of the neurofilament triplet. Eur J Biochem, 1983. 131(1): p. 41-5.
- Ishizaki, Y., M. Kurokawa, and K. Takahashi, A calcium-dependent protease associated with the neural cytoskeleton. Purification and partial characterisation. Eur J Biochem, 1985. 146(2): p. 331-7.
- Vale, R.D., T.S. Reese, and M.P. Sheetz, Identification of a novel force-generating protein, kinesin, involved in microtubule-based motility. Cell, 1985. 42(1): p. 39-50.
- Vale, R.D., et al., Organelle, bead, and microtubule translocations promoted by soluble factors from the squid giant axon. Cell, 1985. 40(3): p. 559-69.
- Ishizaki, Y., et al., Preparation of tubulin from Caulerpa, a marine green alga, using casein as a protective agent against proteolytic degradation. J Biochem, 1988. 104(3): p. 329-32.
- Ebashi, S., et al., Ca2+ regulation in smooth muscle; dissociation of myosin light chain kinase activity from activation of actin-myosin interaction. Prog Clin Biol Res, 1987. 245: p. 109-17.
- Ebashi, S., F. Ebashi, and A. Kodama, Troponin as the Ca++-receptive protein in the contractile system. J Biochem, 1967. 62(1): p. 137-8.
- Raff, M., Looking Back. Annual review of cell and developmental biology, 2011. 27: p. 1-23.
- Raff, M., Theta isoantigen as a marker of thymus-derived lymphocytes in mice. Nature, 1969. 224(5217): p. 378-9.
- de Petris, S. and M.C. Raff, Normal distribution, patching and capping of lymphocyte surface immunoglobulin studied by electron microscopy. Nat New Biol, 1973. 241(113): p. 257-9.
- Raff, M.C., Glial cell diversification in the rat optic nerve. Science, 1989. 243(4897): p. 1450-5.
- Raff, M.C., Social controls on cell survival and cell death. Nature, 1992. 356(6368): p. 397-400.
- Raff, M.C., et al., Programmed cell death and the control of cell survival: lessons from the nervous system. Science, 1993. 262(5134): p. 695-700.
- Ishizaki, Y., et al., Control of lens epithelial cell survival. J Cell Biol, 1993. 121(4): p. 899- 908.
- Ishizaki, Y., J.F. Burne, and M.C. Raff, Autocrine signals enable chondrocytes to survive in culture. J Cell Biol, 1994. 126(4): p. 1069-77.
- Ishizaki, Y., et al., Programmed cell death by default in embryonic cells, fibroblasts, and cancer cells. Mol Biol Cell, 1995. 6(11): p. 1443-58.
- Ishizaki, Y., M.D. Jacobson, and M.C. Raff, A role for caspases in lens fiber differentiation.
J Cell Biol, 1998. 140(1): p. 153-8. - Barres, B.A., et al., Cell death and control of cell survival in the oligodendrocyte lineage. Cell, 1992. 70(1): p. 31-46.
- Raff, M., Ben Barres (1954-2017). Science, 2018. 359(6373): p. 280.
- Allen, N.J., and R. Daneman, In memoriam: Ben Barres. J Cell Biol, 2018. 217(2): p. 435- 8.
【著者プロフィール】
1981 年 3 月 東京大学医学部医学科卒業
1985 年 3 月 東京大学大学院医学系研究科博士課程修了
1985 年〜1987 年 岡崎国立共同研究機構生理学研究所 特別協力研究員、日本学術振興会特別研究員
1987 年〜1992 年 東京医科歯科大学歯学部 助手
1991 年〜1994 年 ユニヴァシティカレッジロンドン生物学部 客員研究員
1992 年〜1997 年 東京医科歯科大学歯学研究科 助手
1997 年〜2001 年 神戸大学医学部 助教授
2001 年〜2004 年 群馬大学医学部 助教授
2004 年〜 群馬大学医学部・医学系研究科 教授
2017 年〜 群馬大学医学部長、医学系研究科長


